不動産広告の歴史を知る【第5回】他国との比較で見る日本独自の不動産広告:駅徒歩○分とマンションポエムの世界
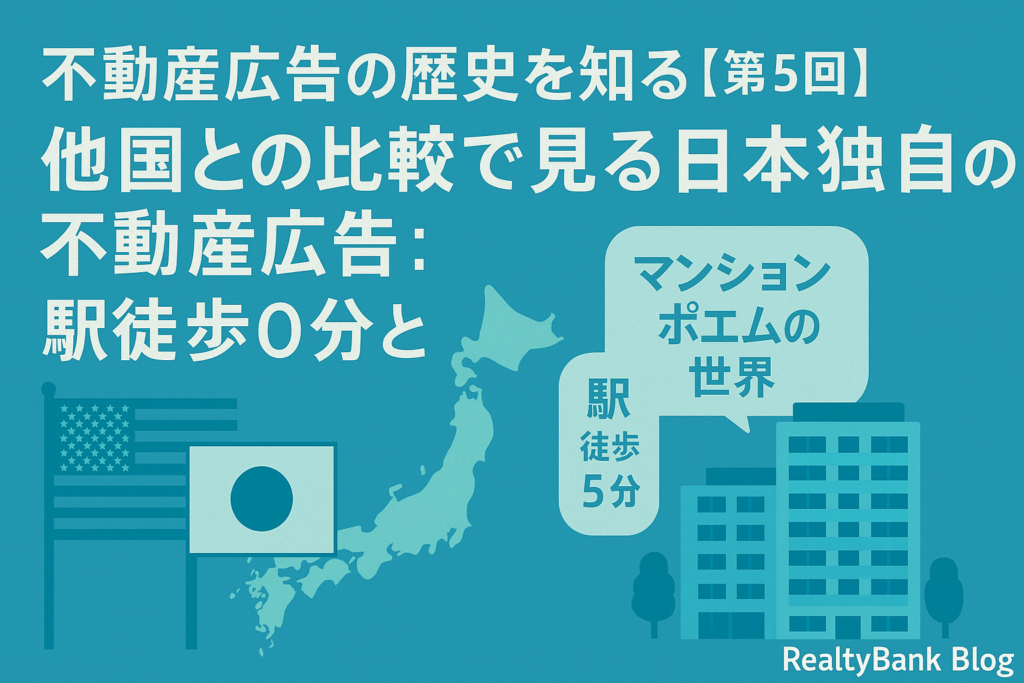
目次
- はじめに
- 海外の不動産広告事情:アメリカ・ヨーロッパ・アジア
- MLS(Multiple Listing Service)の仕組み
- 車社会 vs. 駅近重視の違い
- ビジュアルとデータのバランス
- 日本独自の表現や慣習
- 「駅徒歩○分」ルールの徹底
- 「○○限定」「デザイナーズ」「マンションポエム」
- 規制と文化が融合する日本の広告スタイル
- 公正競争規約がもたらす安心と窮屈さ
- 情緒を大事にする国民性との相性
- 今後の展望:技術革新と国際化の中で
- VRやメタバースで変わる内見体験
- 国際的な基準とのすり合わせ
- まとめ
1. はじめに
どうも、RealtyBank代表の川上です。長らくお送りしてきました「不動産広告の歴史」シリーズ、今回が最終回となります。ここでは、日本の不動産広告を海外と比較しながら、なぜ私たちは「駅徒歩○分」表記を当たり前に使うのか、なぜマンション広告にはポエムのようなフレーズが多いのか、といった日本独自の世界観を掘り下げてみたいと思います。
不動産広告って、「単に物件情報を載せるだけ」じゃないんですよね。その国の文化や法律、消費者の価値観がモロに反映されるので、海外の事例と見比べるとけっこう面白い発見があります。ぜひ最後までお付き合いください!
2. 海外の不動産広告事情:アメリカ・ヨーロッパ・アジア
■ MLS(Multiple Listing Service)の仕組み
まずはアメリカの例から。アメリカでは、不動産会社が物件情報を一元管理する「MLS(Multiple Listing Service)」という仕組みがかなり浸透しています。売りたい人・買いたい人・仲介業者がここに登録して情報を共有することで、不動産広告もMLS上のデータをベースに作られることが多いんですね。ZillowやRealtor.comといったポータルサイトは、MLSのデータを一般消費者向けに見やすく提供しているイメージです。
広告の表現としては、「〇ベッド・〇バス」「□平方フィート」「ガレージ1台分」などのデータを中心に、物件の特徴をストレートに伝える傾向が強いですね。「購入すれば資産価値がこう上がる!」と煽るよりは、「〇〇学区内」「ダウンタウンまで車で15分」など生活の便宜性をアピールする実務的な表現が目立ちます。
■ 車社会 vs. 駅近重視の違い
アメリカやオーストラリアなんかでは車移動が前提なので、日本みたいに「駅徒歩○分」なんて細かい基準はありません。「フリーウェイ何号線まで車で5分」「最寄り駅まで車で15分」とか、そもそも駅が遠いことも多いですしね。
ヨーロッパ各国も公共交通機関は発達しているものの、日本ほど「徒歩時間」を厳密に広告表示する文化は薄いです。「駅近」とざっくり書くか、住所を見て個々で判断するのが普通みたいです。
■ ビジュアルとデータのバランス
欧米の不動産広告は、室内の広さや改装の履歴、築年数などのデータを割とドライに、事実ベースで羅列することが多い印象です。写真もありますが、日本ほど「デザイン性」にこだわる広告は少なく、実際の物件がそのまま写っている感じ。逆に香港やシンガポール、ドバイなんかでは、日本以上に高層マンションの“ゴージャス感”をアピールする広告を目にします。ただ、そういう場合も具体的な広さや価格表記がクリアに示されるので、「雰囲気重視」というよりは「ステータス重視+詳細データ」な感じでしょうか。
3. 日本独自の表現や慣習
■ 「駅徒歩○分」ルールの徹底
日本では不動産広告を見たときに、まず目に入るのが「駅徒歩○分」ってやつですよね。これ、海外から見るとかなり独特だと言われます。しかも「80m=1分、端数切り上げ」という厳密な計算ルールがあって、公正競争規約でも定められている。本当に日本人って電車移動が多いんだなあと改めて思います。
利用者からすれば「駅まで歩いて行けるかどうか」が超重要なので、不動産広告で駅徒歩表示がドーンとくるのは納得なんですけど、海外勢には「こんなに細かく徒歩時間を測るのか」と驚かれることもしばしば。裏を返せば、その表示を期待する消費者が多いからこそ根付いた習慣なんですよね。
■ 「○○限定」「デザイナーズ」「マンションポエム」
日本の不動産広告には「限定」という言葉もやたら多い。「女性限定マンション」「あと○戸限定」「今週末限定内覧会」みたいな煽りが当たり前に見られます。こういう“限定商法”は、日本人が「限定」に弱い(希少価値を感じる)という消費心理をくすぐるんでしょうね。
もうひとつ面白いのが「デザイナーズ」「おしゃれ」「カフェ風」「イマドキ」といった抽象的な表現の乱用。これも日本特有の文化で、シンプルに「リフォーム済み」「内装リノベーション完了」と書くのではなく、ちょっと雰囲気を盛った言い回しが好まれがち。
さらに“マンションポエム”と呼ばれるような詩的コピー(「天空の邸宅」「時を超える優雅さ」など)に至っては、海外にはあまり類を見ないスタイルです。まるで豪華ホテルの紹介文みたいにイメージを膨らませる手法は、日本の「空気を読む」「情緒を大切にする」文化と結びついているのかもしれません。
4. 規制と文化が融合する日本の広告スタイル
■ 公正競争規約がもたらす安心と窮屈さ
日本の不動産広告は「安全パイ」を取るために、かなり細かいルールに従います。最寄り駅の徒歩分数、物件の広さや間取り表記、完成時期など、規定通りに書かないと罰則の対象になることもある。消費者に誤解を与えないという意味では非常に安心できる反面、表現の幅はどうしても制限されます。
海外の広告を見ると、ときに曖昧な言い回しとか、写真と実際が違うじゃん!みたいな事例もあったりして、日本ほどガチガチに縛ってはいない印象です。その代わりトラブルがあれば訴訟になる、といった文化の違いもあるので、一概にどちらが良い悪いという話でもないですけどね。
■ 情緒を大事にする国民性との相性
日本人は「物件の客観的データ」以上に、「ここに住んだらどんな生活が送れるか」といった情緒的な部分を大事にする傾向があります。だからこそ、マンションポエム的な表現や、おしゃれ感・限定感を演出する広告が受け入れられるんだと思います。
もちろん、全員がそうというわけじゃないですよ。でも「周辺環境の雰囲気」「その街のブランド力」「住んだときのイメージ」など、物件そのもの以外の情緒的価値を重視する方が多いのも事実。そのニーズに応える形で、日本の不動産広告は独特の進化を遂げているわけです。
5. 今後の展望:技術革新と国際化の中で
■ VRやメタバースで変わる内見体験
今後、不動産広告はさらにテクノロジーと結びついていくでしょう。VR内見はすでに定着しつつありますし、メタバース空間に物件の仮想モデルを再現して、その中を自由に歩き回れるようにする試みも進んでいます。海外に住む人が日本の物件を購入するときも、わざわざ来日しなくても内見できる未来が近づいているわけですね。
その一方で、法規制やルールはまだ3D空間やメタバースの広告表現に対応しきれていない部分があります。新しいテクノロジーが出るたびに、消費者を守りつつイノベーションを促進するための微妙なバランスが求められます。ここは業界全体の課題になってくるでしょう。
■ 国際的な基準とのすり合わせ
日本の不動産市場も、外国人投資家や海外在住者が物件を購入するケースが増えており、今後はさらにグローバル化が進むと言われています。その中で、海外に合わせた広告表現をどう扱うのかも大きなテーマです。例えば「駅徒歩○分」は日本人向けには必須だけど、海外向けに英語で書くときは「徒歩○分」より「駅まで○m」と書いたほうが伝わりやすいかもしれない。
また、法律や慣習が違う中で、どの程度まで日本独自の規約を適用するのかも課題になりそうです。最近はポータルサイトが多言語対応する動きが出てきていますが、表現ルールや広告デザインの面でも「国際的なスタンダード」と「日本流」の折り合いをどうつけるか、いろいろ試行錯誤が必要になってくると思います。
6. まとめ
これまで5回にわたって「不動産広告の歴史」をお話ししてきました。最後にざっとおさらいすると、戦前~戦後復興期はチラシや新聞広告が中心で素朴な表現が多く、高度成長期には団地ブームとテレビCMが加速、バブル期には豪華絢爛なステータス路線が爆発。そしてバブル崩壊後は実需志向が強まり、インターネットとSNSの普及によって広告媒体が多様化していきました。
そして現在、日本独自の広告表現や規制が根づきつつ、国際化や技術革新の波が押し寄せている。こんな感じの流れですね。
不動産広告って、単なる宣伝ツールに留まらず、その時代や社会、文化を映す鏡のような存在です。今後も社会が変われば広告も変わるし、広告が変わればまた社会の見え方も変わっていくでしょう。僕自身、不動産広告に関わる身として、こうした歴史や国際比較を踏まえながら「どうやってより良い情報発信をしていくか」を常に考えていきたいと思います。
5回シリーズ、最後まで読んでいただきありがとうございました! もし感想やご質問などあれば、ぜひお気軽にコメントいただけると嬉しいです。今後も不動産にまつわる情報を楽しく発信していきますので、引き続きよろしくお願いいたします。
今すぐ、あなたの物件にデジタルステージングを導入してみませんか?
詳細なサービス内容や導入のご相談は、デジタルステージング公式サイトをご覧ください。
実際の導入事例や、簡単な手続きでスタートできる手順も紹介しています。
-より早く!より高く!物件を決める術-デジタルステージング-
株式会社RealtyBank
デジタルステージング事業部
mail:info@digitalstaging.jp
HP:https://digitalstaging.co.jp/lp
Twitter:DStaging2022
Instagram:@dstaging.jp
Facebook:DigitalStaging2022
